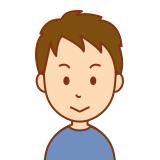
「やらなきゃいけないとわかってるのに、やる気になれない」
この記事では、脳の現状維持機能とその対策を解説します。
脳の現状維持機能を知らないと、動けない自分を「ナマケモノ」と感じてしまうこともあるでしょう。
そして次第に自分を肯定できなくなってしまいます。
この記事を読めば、必要に応じて動けるようになるので、フットワークの軽さが身につくでしょう。
脳の現状維持機能とは

脳の現状維持機能とは、ホメオスタシスともいい、変化をさけようとする脳機能の1つです。
なぜ脳が変化をさけるのかというと、脳にとり、変化がリスクだからですね。
でも今では、変化しない方がリスクだといわれます。
従って「変化がリスク」にはズレを感じる人もいるでしょう。
実は、脳が変化をリスクとするのは大昔の名残です。
脳が現状維持機能を働かせる理由とは
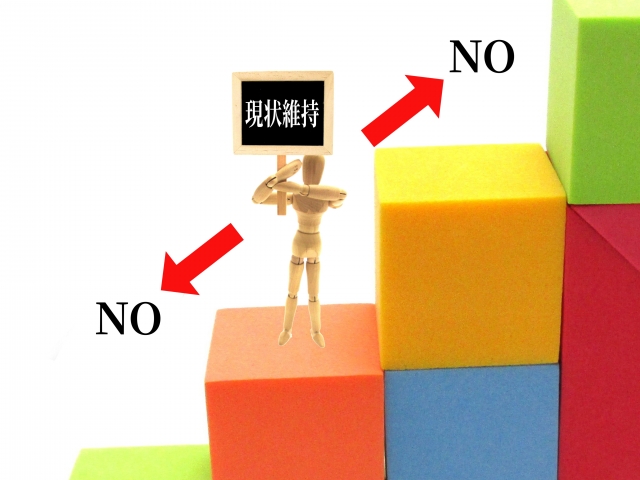
脳が現状維持機能を働かせる理由は、大昔の環境にあります。
数百万年前の狩猟時代、人類にとっては、まさに変化こそリスクでした。
リスクとは、たとえば次のようなものです。
- 今と違う場所にいけば、出会ったことのない猛獣に出会い、殺される
- 食べたことのないものを食べた結果、毒にあたり、命を落とす
結果、脳にとっての生存戦略は、現状維持だとインプットされたのです。
従って現代では、脳の現状維持機能が適切でない場面があります。
我々は脳の現状維持機能を、状況に応じてアジャストする必要があるのです。
脳の現状維持機能が働いた時の3つの対策とは

脳の現状維持機能が働いた時に、現状を変える行動をとるには以下3つの対策が有効です。
- 第一歩を小さくする
- ごほうびを用意する
- 場所を変える
第一歩を小さくする
第一歩を小さくすると、行動しやすくなります。
行動の負荷が減るからですね。
たとえば、勉強しなければならないとき、まず一問だけ解くことを自分に課しましょう。
一問だけなら机に向かいやすくなりますよね。
一問解いたら今日は自分にOKを出して、少しずつ負荷を増やしていくのがコツです。
スモールステップを刻むことで、ムリなく行動できるようになるでしょう。
ごほうびを用意する
ごほうびを用意すると、ごほうびほしさに行動できるようになります。
たとえば「宿題を終えたらケーキを食べて良い」というように、モチベーションにつながるルールを作ってみましょう。
ごほうびが魅力的であればあるほど、行動したくなるはずです。
場所を変える
どうしても家だと気がのらない場合は、場所を変えるのが有効です。
もしかしたら家はリラックスする場所だと、脳が認識している可能性があるからです。
そんなとき、場所を変えるとリラックスモードから切り替えることができます。
オススメの場所は以下の3つ
- 図書館
- 喫茶店
- コワーキングスペース
この3つなら、まわりも勉強や仕事をしていることが多いので、自然とモチベーションも高まるはずです。
まとめ
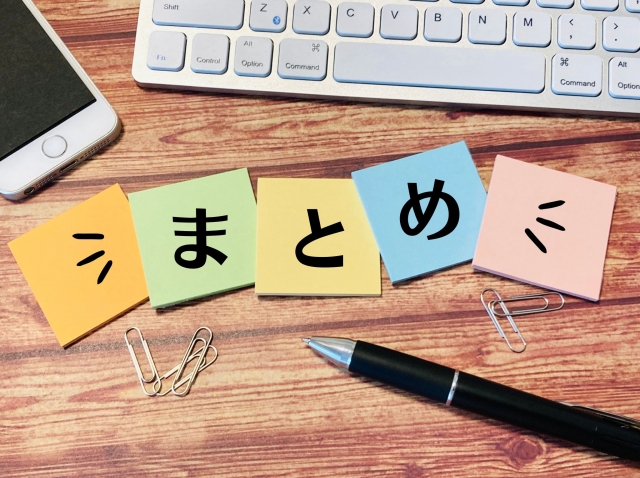
この記事では、脳の現状維持機能とその対策を解説しました。
要点をまとめます。
脳の現状維持機能とは、ホメオスタシスともいい、変化をさけようとする脳機能の1つです。
脳が現状維持機能を働かせる理由は、大昔の環境にあります。
脳の現状維持機能が働いた時に、動くためには以下の3つが有効です。
- 第一歩を小さくする
- ごほうびを用意する
- 場所を変える
脳の現状維持機能は、やり始めが最も強く働きます。
従って、少しずつでも続けていれば、次第に脳の現状維持機能は弱まっていきます。
自転車も、こぎ始めが最も力が要りますが、こいでいけば力が要らなくなるのと一緒ですね。
ぜひ小さくていいので、まず第一歩を踏み出してみてくださいね。



コメント