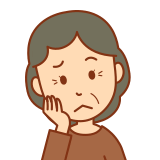
反抗する子にどう対応したらいいんだろう
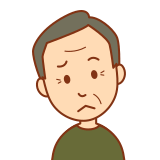
何を言っても聞いてくれない
こんな悩みを抱えていませんか?
実は、デイサービスで児童を預かっていたときの私は、上記セリフを毎日のように心でつぶやいていました。
こんにちは、むらっちです。
結論から、児童との関係はゴードンメソッドを学んだことで解消に向かいました。
そんなゴードンメソッドの一端、能動的な聞き方をこの記事で紹介します。
能動的な聞き方ができないと、子どもはあなたに何かを話そうと思わなくなります。
この記事を読めば、能動的な聞き方が身につくので、子どもはあなたに話をすることで自分で立ち直れるようになるでしょう。
きっと親子関係も改善に向かうようになります。
能動的な聞き方とは

能動的な聞き方とは、話し手が「話を受け取ってくれた」と感じるような聞き方のこと。
たとえば次のような聞き方です。
話し手「今日は学校に行きたくない」
聞き手「そう、今日は学校に行きたくないんだね」
話し手の話を受け止めて、あなたの話はこうだよね、と確認するようにフィードバックしていますね。
これが能動的な聞き方の特徴です。
能動的な聞き方の利点

聞き手が能動的な聞き方をすると、話し手は自ら解決に向けて動き出します。
話を受け取ってくれてると安心するので、次の4ステップを踏むことができるからです。
- ステップ1気持ちが落ち着く
- ステップ2思考が整理される
- ステップ3自分を客観的にみられる
- ステップ4思考が前向きになる
たとえば次のような事例があります。
話し手「今日は学校に行きたくない」
聞き手「そう、今日は学校に行きたくないんだね」
話し手「うん、◯◯が意地悪だからヤダ」
聞き手「そっか、◯◯に意地悪されるのが嫌なんだ」
話し手「だから学童だけいく……でもそれじゃズル休みしたと言われるかな……やっぱり学校行く」
実はこの能動的聞き方はカウンセラーのスキルの1つです。
カウンセリングでは、クライアントが自ら立ち直るように、能動的に話を聞いていきます。
同様に我々が能動的な聞き方をすることで、話し手を自ら解決に向けることができるのです。
まとめ
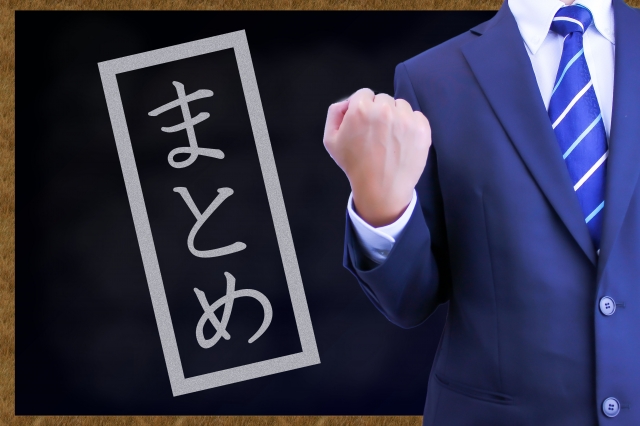
この記事では、子どもと良い関係を結べる能動的な聞き方を解説しました。
要点をまとめます。
能動的な聞き方とは、話し手が「話を受け取ってくれた」と感じるような聞き方のこと。
聞き手が能動的な聞き方をすると、話し手は自ら解決に向けて動き出します。
子どもの話を聞くのは難しく、つい解釈してしまいがちです。
私もつい解決策を提示してみたり、意見を言ったりしていました。
その意味で、能動的聞き方をするためには、聞くことの意識が大切ですね。
そしてアドバイスよりも、相手自身の解決力を信じるのが肝でしょう。
能動的聞き方、ぜひ使ってみてくださいね。



コメント